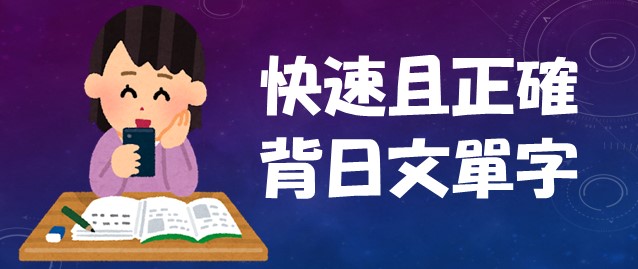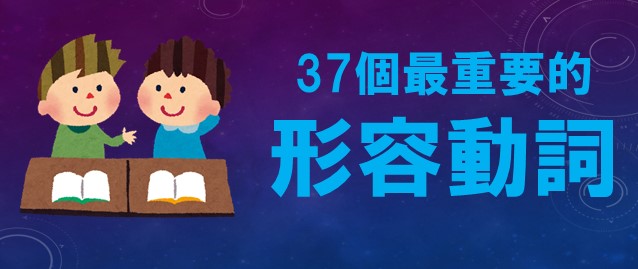日語免費線上課程日語的連濁什麼時候要唸成濁音?日本國立國語研究所窪薗晴夫教授演講
今日のこの講義では、音韻構造と文法・意味構造との関係を検討してみたいと思います
言語の研究にはこのような様々な分野があります
音声学・音韻論のような音声の研究
形態論・語形成論の語の研究
統語論あるいは文法論と呼ばれる文の研究
意味論・語用論などの意味の研究です
今日の講義では、特にこの音声の研究を中心に
この音声の現象が、
他の分野の
構造、原理とどのように関わっているか?ということを
考察してみます
講義のあらすじは、このような内容です
まず最初に、今日の一番のテーマであります連濁という音声現象が
どのようなものであるか?ということを解説いたします
その次に、その連濁の現象にどのような条件や制約がかかるかということ
とりわけ、意味の構造や語の内部構造に
どのように関係しているか?ということをお話しいたします
そしてその後で、この連濁に見られる様々な制約が、
他の現象、
例えば、日本語の複合語アクセントにどのように見られるのか?
さらに、他の言語にも見られるということを指摘してみます
連濁という現象は、日本語によく見られる現象ですけれども
複合語の後ろの要素が濁る現象です
もう少し、専門的に言いますと
複合語において、
後部要素の最初の子音が、無声子音から有声子音に変化する現象
例えば、「棚」という言葉は「本棚」「戸棚」のような複合語の中で
タナからダナに変わります
つまり、タ行音がダ行音に変わります
同様に、「亀」という単語も
「海亀」「ミドリガメ」のように、カメからガメ
つまり、カ行音がガ行音に変わります
「魚」も「生魚」「煮魚」のように、
サ行音がザ行音に変わり
「箱」も「靴箱」「玉手箱」のように、
ハ行音がバ行音に変わります
このように、複合語の後ろの要素の最初の子音が
無声音から有声音に変わる
声帯が振動するようになる
これが、連濁と呼ばれる現象です
この連濁の現象は、日本語ではとても生産的に起こるものです
例えば、人名を見てみますと、
ここに挙げたのは、日本の苗字のトップ20ですけれども
その中に、「山田」「吉田」「山口」などの連濁を起こす単語があります
「山田」「吉田」では、タがダに変わり、
「山口」は、クチがグチに変わっています
地名にも、この連濁の現象はたくさんあります
都道府県名を見てみましても
「新潟」「栃木」「千葉」「神奈川」「山口」「香川」「宮崎」のようなものがあって
「潟」や「木」「川」「崎」というものが
それぞれ、ガタ、ギ、ガワ、ザキというふうに濁っています
これが、連濁の現象です
ところが、連濁の研究で一番大きな問題が
どういう条件の時に濁って、どういうときに濁らないか?ということです
ここに示した、左側の語が濁るものですけれども
例えば、「巻き貝」という貝殻の「貝」は濁りますが、
パーティーの「会」は、濁りません
「新年会」「忘年会」のように
あるいは、「海亀」の「亀」は濁りますが、
「カメラ」は、デジタルガメラにならない
さらに子供の「子」というのは、
「乳飲み子」では濁るけれども、「一人っ子」になると濁らない
「菓子」という言葉は、
「和菓子」「洋菓子」のように濁りますけれども、
「火事」という言葉は、濁らない
山ガジにはならない
繰り返す言葉でも
「とき」が繰り返して、「ときどき」とは濁りますけれども
「しば」は、しばジバにはならずに、しばシバになる
人の名前で中ジマ、これは中シマ、両方発音がありますけれども
この名前は、長シマであって長ジマにはなりにくい
あるいは、同じ「書き」という言葉でも、
「宛名書き」は濁りますけれども、「読み書き」は濁らない
「白」という単語は、
「尾白鷲」の中では濁りますが、「紋白蝶」では濁らない
あるいは、千円二千円の「千」という言葉も
「三千円」では、センがゼンになりますけれども
「二千円」では、二ゼン円にはならない
こういうふうに、
連濁する場合と、連濁しない場合があって
どういう条件の下で連濁が起こるのか?
これが、連濁をめぐる研究の中では、
一番大きな課題となっているわけです
今日は先行研究を基にして、
この連濁が起こる条件を、いくつかお話したいと思います
まず最初の条件は、語種に関係するものです
例えば、貝殻の「貝」は濁りますが、
パーティーの「会」は、「忘年会」「新年会」のように濁りません
「海亀」は濁りますけれども、
「デジタルカメラ」はデジタルガメラにはならない
これがなぜか?というのが、語種と関係してきます
語種というのは、語彙層とも言いますが
日本語の中では、昔から日本語にある和語、大和言葉と
中国語から入ってきた漢語
そして、それ以外の外国語
例えば、英語、ポルトガル語から入ってきたカタカナ語などがあります
この三つの層が、あるわけです
例えば、数字を見てみますと、
「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」というのは、大和言葉、和語です
「いち」「に」「さん」というのは、漢語です
そして、「ワン」「ツー」「スリー」というのは、英語から入ってきた外来語です
これが、連濁と大いに関係がありまして、
一般に和語は、連濁を起こしやすいと言われています
子供の「子」は、「乳飲み子」「みなし子」のように濁りますし
貝殻の「貝」も、「二枚貝」「巻き貝」のように濁ります
「亀」も濁ります
ところが、同じコであっても「湖」のコは
「琵琶湖」「河口湖」のように、濁りません
そして、パーティーの「会」も「忘年会」「新年会」のように濁りません
漢語の場合は、大体10%ぐらいしか濁らないと言われています
つまり、90%パーセントは連濁を起こさないというわけです
その10%の中の例外として、挙げられているのが
例えば「食用菊」のギク、「比叡山」のザン、「文庫本」のボン、
「砂糖」が「白砂糖」「黒砂糖」のように濁る現象
「菓子」が「洋菓子」「和菓子」のように濁る現象
これが、10%の例外の中に入っているものです
外来語になりますと、さらに連濁は起こりにくくなります
「カメラ」は、決してデジタルガメラにはなりませんし
「テープ」も、 粘着デープとはなりません
数少ない例外が、日本語の中に古くからある外来語
例えば「カルタ」「カッパ」のような、ポルトガル語から入ってきた言葉は
「いろはガルタ」「あまがっぱ」のように濁りますけれども
これは、数少ない例外です
このようにして、和語は濁りやすい、漢語は濁りにくい、
そして、外来語は、ほとんど濁らないということが言われています
連濁の条件の二つ目として、
促音の「っ」との関係を挙げることができます
例えば、「乳飲み子」「みなし子」は濁りますけれども
同じ「子」でも「江戸っ子」「一人っ子」「東京っ子」というのは濁りません
これは、「子」の前に「っ」という促音があるからです
すなわち、促音の後は濁らないということがわかります
これは、言語学ではNo Voiced Geminateと言われる制約でして
非常に広範囲に、日本語だけではなくて他の言語にも見られるものです
日本語の中でも例えば、ただ一人の「ただ」というのを
もう少し強調して「たった」一人となると、今度は濁らなくなる
つまり、促音の「っ」が入ったことによって濁りがなくなると
濁音がなくなるという現象です
東北地方では、文末で、
そうだべ、のように「だべ」という言葉がありますが
これは、茨城方言では、そう「だっぺ」となります
つまり「っ」が入ると同時に、この濁音のベが消えてしまうという現象です
このようにして、促音と濁音というのは、共起しにくいということが言われています
連濁の条件の三つ目が、ライマンの法則と言われるものです
これは非常に強い制限でして、例えばこの左の方の単語は
「和菓子」「ときどき」「鍋蓋」「渋柿」のように濁るものですけれども
右の方の「火事」「しば」「札」「鍵」というのは、濁りません
つまり「山火事」は、山ガジにはならず
「しばしば」も、しばジバにはならず
「札」も「赤札」になって、赤ブダにはならない
「鍵」の場合も「合鍵」であって、合ガギではないということです
この左のグループと、右の方のグループを、比較してみますと
右のグループには、最初から濁音があることがわかります
つまり、「火事」というのは「菓子」とは違って
最初から、ジという濁音を持っているわけです
「しば」「札」「鍵」も、同様です
このようにすでに濁音を持った語は、連濁を起こしにくいということがわかります
これが、ライマンの法則というものです
すなわち、同じ語の中に濁音は二回出てこない、
連続して出てこないという現象です
ただ、いくつか例外はあるのですが
例えば、「避難梯子」という「梯子」という単語は
避難ハシゴという発音とあわせて、
避難バシゴという発音も、観察されます
ここでは、濁音のゴがあるにもかかわらず、連濁を起こしているという、
ライマンの法則の例外となるものです
ちなみに、このライマンというのは
明治初期に日本に来ました、アメリカ人の
Benjamin Lymanという人の名前からとられています
このライマンの法則は、様々なところに見られる現象です
例えば「中島」という名前は、 中シマと両方ありますけれども
「長島」は、決して長ジマにはなりません
あるいは「島田」は濁りますが、「柴田」は濁らない
「たき火」は濁るけれども「飛び火」は濁らない
「片づける」は濁りますが「傷つける」は濁らない
「表示」「展示」の「示」は、シがジに濁りますが
「図示」は濁らない
こういうふうにして、
この場合には、複合語の前の要素の最後
つまり「長」のガ、「柴」のバ、「飛び」のビ
こういうふうに、複合語の前の要素が濁音である場合には、濁らないというものです
これも同じライマンの法則の名前で捉えられています
同じ語の中で、濁音の後ろにさらに濁音は生じない、という現象です
ただ、ここまでいきますと少々例外が多くなりまして
例えば、私の名前は「窪薗」ですけれども
「窪」という濁音で終わりながら、
ソノがゾノに変わっています
同じように「溝口」「長渕」「鍋蓋」のように
濁音で終わる単語の後ろに続いても濁音が生じる
連濁が生じるという、
これはライマンの法則の例外です
連濁の条件の四つ目が、意味構造との関係です
並列構造で、連濁が起こりにくいと言われています
例えば、「宛名書き」「下書き」は濁りますが
「読み書き」になると濁りません
読みガキにはならない
「日帰り」「仕事帰り」では「帰り」は濁りますが、
「行き帰り」は、濁りません
「大食い」「やけ食い」では濁っても、「飲み食い」では飲みグイにはならない
さらに「負けず嫌い」「食べず嫌い」のように
「嫌い」という言葉は濁ることが多いわけですけれども
「好き嫌い」では、濁らない
「鷲鼻」「団子鼻」は濁りますが
「目鼻」というのでは濁らない
「逃げ腰」「へっぴり腰」では、濁るけれども
「足腰」では、濁らない
この濁らないものを見てみますと、共通点が見えてきます
「読み書き」「行き帰り」のように
二つのものが、並列の関係で並んできています
つまり、A&Bという構造を作っているものです
このような構造を、並列構造と言いますけれども
並列構造の場合には、連濁が起こらなくなるということがわかるわけです
別の言い方をしますと、
連濁が起こらないことによって、普通の修飾構造を作らないということを表す、
このような特殊な意味構造を持っているということを、示すわけです
この並列構造も、様々なところに見られます
例えば、同じ複合語のように見えても
「山川」、「山の川」は山ガワと濁るけれども
「山」と「川」であれば、山カワとなって、山ガワにはならない
あるいは、「谷の川」は濁るけれども、
「谷」と「川」、並列構造になると、谷カワになって濁らない
「尾のひれ」は、尾ビレと濁るけれども、
「尾」と「ひれ」であると、並列構造だから、尾ヒレのままであると
このようなものです
さらに、例えば「寄木」では、「木」が濁りますが、
「草木」では濁らない
「水不足」は、フソクがブソクになりますが、
「過不足」は、過ブソクとはならない
これは、過フソクのままである
「ざりがに」の合戦の場合でも、
「ざりがに合戦」は、ありえますけれども
「さるかに」の場合には、「さる」と「かに」が並列構造ですので、濁らない
「大太鼓」「小太鼓」は、タイコがダイコと濁りますけれども
「笛太鼓」、五人囃子の「笛太鼓」の場合には、濁らないというものです
もっとも、合唱団によっては
笛ダイコというふうに発音し、連濁を起こすところもありますが、
これは、「笛」と「太鼓」という並列の構造が、わからなくなった
意識されなくなった結果だと、考えられています
連濁の五つ目の条件が、枝分かれ構造です
例えば、同じ「白」でも
「尾白鷲」は、シロがジロと濁りますけれども
「紋白蝶」は濁りません
紋ジロ蝶には、ならない
これはなぜかと言いますと、その構造を考えてみるとよくわかります
「尾白鷲」は、尾が白い鷲です
「尾」が「白」を修飾しています
ところが、「紋白蝶」の場合には、紋が白いわけではありません
紋白蝶というのは、紋のついた白蝶です
つまり「紋」は、「白蝶」を修飾するのであって、
「白」だけを修飾しているわけではありません
こういうふうにして、修飾関係にない場合
言語学では、こちらを左枝分かれ構造、
こちらを、右枝分かれ構造と言いますけれども
右枝分かれ構造の場合には、そこでこの連濁の規則がブロックされてしまうわけです
言語学の教科書を見てみますと、このような例が出てきます
塗りバシ入れと、塗りハシ入れ、にせダヌキ汁と、にせタヌキ汁
左の方は、「塗り」が「箸」を修飾して、「にせ」が「狸」を修飾する
つまり、漆を塗ってあるのは何か?というと
「箸」を塗ってあるか、あるいは「箸入れ」を塗ってあるか
それによって、濁るか濁らないかが変わる
こちらの場合でも、「にせ」なのは「タヌキ」なのか「タヌキ汁」なのか
その構造によって、右枝分かれ場合には、このところで連濁が阻止されて
それぞれ塗りハシ入れとか、にせタヌキ汁のようになるという現象です
連濁には、地域差も関係しているのではないか?ということもよく言われます
つまり、連濁を好む地域と、好まない地域があるのではないか
ただ、これにつきましては研究がまだ進んでおりません
例えば、中ダと発音するか、中タなのか
中ジマなのか、中シマなのか、そこに地域差があるのではないかという考え方です
確かに「植田」というのを見てみますと、
これは鳥取県の一部では上タというふうに濁らなくなりますので
そういう地域が、あるような気がいたします
あるいは、研究ジョと発音するか、研究ショと発音するか
これも私の印象では、関東のかたは研究ジョと濁って
関西のかたは、研究ショと濁らない傾向があるように見られます
「裁判所」にしても東京の年配の方々の中には
裁判ジョと濁る人もいらっしゃるようです
「切り貼り」という言葉も、関西の方々は、切りハリが多くて
関東のかたは、切りバリというふうに濁ることが多いようです
ただ先ほど言いましたように、これにつきましては研究がまだ進んでおりませんで
日本全国で、どの地域が連濁を起こしやすくて
どの地域が起こしにくいかということについては、わかりません
もし、このアホバカ分布図のような地図を描くことができれば
面白いと思いますけれども
この図は、「アホ」と言うか「バカ」と言うかというのを
各地で調べてその分布を示したもので
この「アホ」と言う地域は大体関西を中心に、京都を中心に分布していて
それを取り巻くような形で「バカ」の地域が分布しています
連濁につきましても、このようにどの地域が連濁を起こしやすい
どの地域が連濁を起こしにくいということが、わかればいいのですけれども
残念ながら、今のところわかっておりません
連濁を起こしやすくするか、起こしにくくするか
その七つ目の条件として撥音の「ん」を挙げることができます
これまで見た条件は、だいたい連濁を起こしにくくする条件でしたけれども
この条件だけは、連濁を起こしやすくする条件です
例えば「千」「本」「藤」「国」、これは漢語です
つまり漢字の音読みです
ですので、基本的に連濁を起こさないのが、普通なわけですけれども
ところが「三千円」「三本」「近藤」「安藤」「権藤」
あるいは「本国」「隣国」「戦国」のように、連濁を起こすものが出てきます
これを見てみますと
三千円の「三」、近藤の「近」、本国の「本」のように
前の要素が、撥音の「ん」で終わっていることがわかります
つまり、撥音の「ん」の後ろでは、連濁が起こりやすいことがわかるわけです
一方、こちらのグループは
二千円の「二」とか佐藤の「佐」、外国の「外」のように
最初の要素が、撥音の「ん」で終わっておりません
それで、連濁を起こさないというわけです
この撥音の後ろで連濁が起こりやすいという現象は、
日本語だけではなく他の言語でも観察されています
post-nasal voicingという名前で呼ばれていますけれども
鼻音の後では連濁が、濁音が起こりやすくなるというものです
ちなみに「四千円」とか「四本」では前の要素が「ん」で終わっているにも関わらず
連濁を起こさないグループに入る
これなぜかということがわかりますが
もともとこのヨンというのは後から出てきた発音で
わかりますように、いち、に、さん、よん、ご、というのは漢語で
もともとこれはヨン本ではなくてシ本という発音をしていました
ですから、この連濁を起こす条件を満たしていなかったわけです
ここまでのまとめを見てみますと
この連濁という音韻現象には様々な条件・制約が働いているということがわかります
語種からはじまりまして
促音、ライマンの法則、意味構造、枝分かれ構造、撥音の「ん」
こういう条件を見てきました
特に、連濁という音韻規則が
意味構造や枝分かれ構造と 大きく関係しているということが、分かったわけです
そこで出てきます次の問題が
果たしてこういうふうな制限を受ける現象は、連濁だけなのかと
他にないのか?ということが疑問になってきます
最後に、この話をしたいと思います
連濁と同じように、複合語によく出てくるものがアクセントの現象で
例えば、「ヤマト」と「ナデシコ」で「大和撫子」
「サッカー」と「クラブ」で「サッカークラブ」
「日本」と「銀行」で「日本銀行」
「国立」と「大学」で「国立大学」のように
複合語になるとアクセントが一つの山にまとまります
これは連濁と同じように
二つの要素を一つにまとめようとして、こういう現象が起こるわけです
ところが興味深いことに、並列構造ではその現象が起こりません
つまりアクセントの規則が、阻止されてしまいます
「チェコ」「スロバキア」というのは決して「チェコスロバキア」にはならず
あるいは「びっくり」「仰天」というのも「びっくり仰天」にはなりません
これはなぜかといいますと、
チェコスロバキアは「チェコ」と「スロバキア」と二つの地域が一緒になった国でした
あるいはびっくり仰天も
「びっくり」と「仰天」、同じ意味のものが、並列の関係で並んでいます
「一夫多妻」「相思相愛」「春夏秋冬」「公平中立」
全て、ここに挙げた例は並列構造を作っています
このような複合語では、複合語のアクセントの規則が阻止されてしまいます
つまりアクセントが一つにまとまらずに、
それぞれの要素が、ばらばらの発音をするわけです
これは、さきほど連濁の時に見ました「読み書き」と同じ現象です
つまり「読み書き」も並列構造であって、そして連濁が起こらない
同じように「チェコスロバキア」も並列構造であって、
複合語のアクセントが一つにならないという現象です
さらに興味深いことに、同じ制約が英語にも観察されています
英語のアクセントは、日本語とちょっと違っておりまして
高さのアクセントではなくて、強さのアクセントだと言われています
そのために、
例えばblackとboard、黒と板ですけれども
それが一つにまとまった時に、黒板 BLACK boardという発音が出てきます
強・弱という発音が出てくるわけです
つまり、英語の場合には
後ろの要素を弱くすることによって、二つの単語を一つにまとめようとしています
これに対しまして、ただ単語が続いたときの名詞句では、
黒い板 BLACK BOARD
両方の要素が、それぞれ強く
あるいは、若干前のほうが弱くなって
決して、前のほうが強くて後ろのほうが弱いという
BLACK boardの構造を、とらないわけです
英語には、このような複合語がたくさんあります
White House、green house、English teacher、woman doctor、dancing girl
このような複合語がたくさんあるわけです
いずれも、前の要素が強くて後ろの要素が弱くなる
それによって、一つにまとまっているわけです
ところが、日本語の場合と同じように 並列の構造になってきますと、
一つにまとまらなくなります
例えば、Coca Colaという単語があります
これは決して、COCA colaとはなりません
なぜかと言いますと、
この飲み物は、
cocaという植物と、colaという植物の
それぞれの葉と実から作られた飲み物です
つまり、cocaという単語とcolaという単語が
並列構造を持っているわけです
同じように、Czechoslovakiaという単語
あるいは、
producer-director、king-emperor、historian-politician、secretary-treasurer
このような単語は、AとBという関係を作っています
並列構造を作っていますので、
決して、強・弱の構造にはならずに
それぞれの要素が、アクセントを保つというものです
あるいは日本語にもなっていますが、
「PTA」という単語は、parent-teacher association
つまり、父兄と教師が作る associationですが
ここでも、普通の PARENT teacher associationという複合語の構造は出てきません
つまり、parentとteacherが並列構造のために、
そこで、複合語のアクセント規則が、阻止されているわけです
このような並列構造によって、
アクセントの規則、あるいは音韻規則が阻止されるという現象は
韓国語やその他の言語でも、様々報告されています
最後に、枝分かれ構造と複合語アクセントの関係を見てみます
ここで出しました例は「赤白饅頭」と「紅白歌合戦」です
紅白饅頭は、「紅白」と「饅頭」で一つにまとまって
紅白饅頭というアクセントの山を作ります
それに対して、紅白歌合戦の場合には、
紅白」と「歌合戦」は一つにまとまりません
紅白歌合戦とならずに、
紅白が、他の要素と切れてしまいます
つまり、ここのところで
複合語のアクセントの規則が、阻止されるわけです
これは、修飾関係を見るとよくわかります
紅白饅頭は「紅白」が「饅頭」を修飾しますが
紅白歌合戦は、「紅白」が修飾するのは「歌合戦」であって、
決して「歌」ではありません
このような右枝分かれの場合には、
この複合語のアクセントの規則が、阻止されているわけです
この現象は、先程見ました「紋白蝶」と同じものです
右枝分かれ構造の時には、
連濁の規則が阻止されるということを見ましたけれども
ここでは、複合語アクセントに全く同じ現象が見られています
さらに、同じ制約が英語の複合語にも見られます
EVENING class instructor
夜間の授業の教師
この場合には、
BLACK boardと同じように、普通の複合語規則が働きまして
一番最初が強くなって、あとが弱くなります
ところが、EVENING COMPUTER classという単語
これは「夜間のコンピューター」ではなくて
「夜間の」「コンピューターの授業」という意味です
右枝分かれ構造で、
「夜間」は、「コンピューター」ではなくて「コンピューターの授業」全体を修飾しています
このような構造の時には、複合語の規則がここで阻止されてしまう
日本語と同じ現象が見られるわけです
この現象は、他の言語でも見られて、報告されています
中国語のtone sandhiの現象、
あるいは、イタリア語の語頭子音の長音化
あるいは、アフリカの言語のエウェ語に見られる声調の規則
このような様々なところで
日本語や英語と同じ現象が見られるわけです
以上のことをまとめてみますと、
連濁という音韻現象に、様々な条件が関わることを、まず見ました
そして、その連濁規則は、
特に、意味構造や枝分かれ構造と大きく関係している
制限を受けているということを、お話ししました
さらに、面白いことに、その同じ条件が
連濁ではなくして、複合語アクセントにも見られるということを、お話ししました
今日は、お話する時間がありませんけれども
イントネーションなどの現象にも、同じ原理が働いています
さらに同じ条件が、
英語や韓国語など他の言語にも、観察されるということがわかっています
このようにして、音韻現象というのは
意味構造や語の内部構造など
他の部門の構造と、大きく関わっているということがわかるわけです
以上で、今日の講義を終わります
-250x80.jpg)
/言語学レクチャーシリーズVol-1-YouTube-1024x518.png)